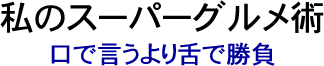
“蕎麦屋酒”の著者がプロ顔負けの美味探求
|
第726回 このコラム執筆も今週いっぱいとなった。 美味しさを探求して源流を遡り、 現在、農薬を使うことへの危機感は 栃木県馬頭ののどかな里山のなかで蕎麦を手作りで育てて、 昨年の春から開始した椎茸の原木栽培は、 |
| ←前回記事へ |
2007年7月2日(月) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
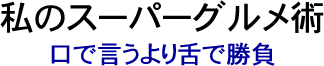
“蕎麦屋酒”の著者がプロ顔負けの美味探求
|
第726回 このコラム執筆も今週いっぱいとなった。 美味しさを探求して源流を遡り、 現在、農薬を使うことへの危機感は 栃木県馬頭ののどかな里山のなかで蕎麦を手作りで育てて、 昨年の春から開始した椎茸の原木栽培は、 |
| ←前回記事へ |
2007年7月2日(月) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |