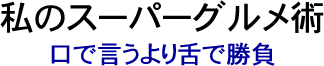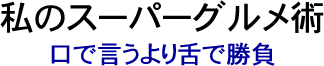|
第312回
SSIの分類や全国新酒鑑評会は品質基準とはならない
日本酒の特性を表現するものには、
日本酒造組合中央会が
SSI(日本酒サービス協会・酒匠研究会連合会)
に依頼して作成した、
味の濃さと香りの強さによる2軸の特性表示が提案されている。
しかし、この2軸のどこに酒があるとしても、
その酒の特性の一部が表現されているだけで、
旨いかまずいかの品質基準とは一切関係がない。
だいたい、SSIの進めている日本酒の味わい分類法は、
もともとワイン業界のソムリエたちの知恵の範囲であって、
日本酒独特の燗酒の味わい、熟成過程による味乗りなどの、
伝統的な食文化の叡智に欠けている。
では、「全国新酒鑑評会」はどうか?
これは、昔の国税局醸造試験場、
今では、独立行政法人酒類研究所が主催する大規模な鑑評会で、
出品する日本酒の仕様は吟醸酒で、
原料が50%以上山田錦を用いているかどうかで、
二つの区分に分けられている。
そして、評価は味・香りによる官能評価。
つまり、製造方法についての基準は設けられておらず、
評価委員が味と香り、
あるいは、色などを見て感覚的に判断するものだ。
しかも、評価対象となるものは、香りが一番、
それに、雑味、雑香などがでていないことという
マイナス評価が主体となる。
全国新酒鑑評会は
酒を造る蔵人たちのやる気を起こさせるという意味では、
日本酒業界に貢献しているが、
カプロン酸ぷんぷんの吟醸酒が
もてはやされるようになった元凶でもある。
ワインでは11月なかばには、
ボージョレーヌーボーが出荷されるが、
日本酒の全国新酒鑑評会は、
このボージョレーヌーボーのような
新酒の状態で評価しているようなものだ。
熟成による旨みが乗っていく可能性などは
評価対象には入っていない。
日本酒では、ワインのような原産地呼称法のような、
品質そのものを基準化するという動きは過去にはほとんどなく、
今後もでてきそうもない。
|