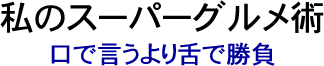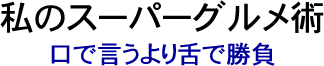|
第139回
花見は日本文化の原点
寒風が吹くなかで、街路樹の芽が膨らんできている。
そろそろ、梅が咲き始め、桜も待ち遠しくなってくる頃だ。
現在は、桜が梅よりも人気が高いようだが、
もともとの花見は梅が桜よりも高貴とされていたようだ。
日本での花見は、
もともとはその年の稲の稔りを占うことで行われていた。
花のつきかたで豊作かどうかを神から教えてもらう。
そのときに、神に近づくために酒を飲み、
精神的な高揚を感じる、というわけだ。
極めて神聖な行事であったわけである。
飛鳥、平安の頃は梅の花見が普通だったようだが、
万葉集などに桜の花見の記述がある歌はあるので、
桜も徐々に花見をするようになっていったと推測されている。
桜の花見が大々的に行われたイベントとしては、
豊臣秀吉の醍醐の花見が有名だ。
醍醐は今でも醍醐寺の敷地は山になっていて、
下から桜前線が登っていく。
満開の頃は素晴しいらしいが、
私が一度訪問したときは、
残念ながらふもとで2分咲きくらいであった。
東京の桜の時季に比べて
1週間程度遅いということを知らずに訪れた結果だった。
庶民が花見をするようになったのは江戸の頃で、
ハレの日として弁当を持参して宴会を行うようになっていった。
これが現在に通ずるわけだ。
で、私自身花見は大好きで、毎年数回の花見に参加している。
多い年だと5回花見を行い、
そのうち昼は宇都宮の八幡山公園、
夜は埼玉県白子の理化学研究所と、
1日で2回花見の場所を移して連荘したこともある。
花見で愉しくすごすには、場所の問題もあるが、
十分に酒と肴を準備することだ。
さらに、火を使ったりして、
焼き物、鍋、燗酒などを愉しむのもとてもいい。
また、料理店の弁当を事前に予約して
持っていくのもバリエーションができる。
私が自分で企画する花見は3月の初めころから
どのようなイメージで、どこで開催するかを考えて、
料理を決める。
下ごしらえをしておけば、
現地であまり手をかけない料理を選ぶ。
昨年開催した花見では、
魚介類と鴨のBBQ、湯豆腐、お造りを自前で現地で作り、
江戸前鮨屋の「ばらちらし」、
割烹料理屋の「花見用特別弁当」を少量仕入れておいた。
酒はもちろん日本酒を数種類。お燗をする。
場所は桜が綺麗なことはもちろん、
火を使えて、あまり混まないところ、
そして、交通の便がよいところが理想だ。
実は、都内でも無名の花見の場所は結構いっぱい残されている。
我々が夜桜で利用する場所は平日だと、
混雑率が20%程度で、まわりのグループが全然気にならない。
花見も、漠然とやるよりは、
計画性を持ってやったほうが、断然美味しい。
|