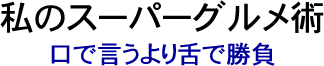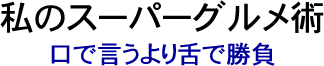|
第50回
江戸前の蕎麦屋は粋が命
江戸前というのは鰻屋から始まったようだ。
江戸の川でとれた鰻は、
旅してきた鰻とは一線を画すという意味合いで使ったようだ。
江戸前という言葉は蕎麦や鮨にも伝わった。
鮨の場合は江戸の前の海、
すなわち東京湾でとれる魚に対して称するわけだが、
蕎麦だと江戸風という意味になる。
江戸風の蕎麦というのは、田舎の打ち方とは違って、
綺麗に四角形に延ばして蕎麦の長さを揃えてきるという
江戸の伝統の蕎麦打ち技術がベースとなっているが、
その他に江戸の粋を持っている蕎麦屋を指して言う意味合いもある。
この江戸の粋を満喫できる蕎麦屋が
静岡県の島田にある「藪蕎麦宮本」だ。
店主の宮本晨一郎さんは、
藪御三家のうちの一つの「池之端藪蕎麦」で
親方から江戸前の心意気を徹底的に叩き込まれて、
静岡に戻ってきた。
「藪蕎麦宮本」は無駄を省いた清楚な店内で
宮本さんが一人で造る料理と蕎麦を堪能することになる。
特に玄蕎麦を手挽きの石臼で挽いた粉を使った田舎蕎麦は、
田舎のおばちゃんが太く打つ田舎蕎麦とは全く違い、
輪郭がはっきりとしていて
蕎麦の香りと味を本当に楽しめる逸品だ。
江戸前の粋を感じながら
美味しい蕎麦を満喫できる店は他にもある。
群馬県箕輪「せきざわ」、
穂高「大梅」、
神楽坂「たかさご」、
中村「野中」はいずれも玄蕎麦から仕入れて、
皮むき、製粉をし、美味しい蕎麦切りを提供してくれる。
他にもニューウェイブの粗挽き蕎麦にこだわる店、
料理屋からの転進の店、などいい蕎麦屋は挙げれば切がないが、
拙書「蕎麦屋酒」の蕎麦屋ガイドの部分を参照していただきたい。
たかが蕎麦と思われる方もいるだろうが、
蕎麦こそ美食の小宇宙なのである。
|