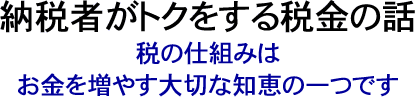|
第49回 生前贈与のための新相続税制
新制度理解のために
「相続税の仕組み(2) ― 相続税は累進税率」
亡くなった人の土地、家屋、預貯金、
株式などの有価証券、家財道具など
お金に見積もることができる財産は
すべて相続税の対象になります。
また、死亡保険金や死亡退職金にも相続税がかかります。
但し、亡くなった人の借入金や
未払い税金などの債務と葬式費用は、
これらの相続財産から控除することができます。
つまり、亡くなった人のプラスの財産から
マイナスの財産を差し引いたところの正味財産(図1-A部分)が、
基礎控除額を越えた場合、
超えた部分(図1-B部分)に相続税がかかるのです。
相続税は次の
【ステップ1】〜【ステップ4】の順に計算して求めます。
【ステップ1】
亡くなった人の正味財産のうち
基礎控除を超える部分の金額(図1-B)を、
法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して
按分計算します(図1のC〜E)。
(相続税の計算上按分計算するだけであり、
実際の遺産分割とは関係ありません)
【ステップ2】
仮の按分計算後の各法定相続人ごとの
計算上の取得金額(図1のC〜E)に、
それぞれ相続税の税率を乗じて相続税を計算します。
【ステップ3】
ステップ2で計算した相続税を合計して
相続税の総額(図1-F)を計算します。
【ステップ4】
相続税の総額を、各人が取得した正味財産の割合で按分して
各人の負担額を計算します。
なお、配偶者には税額を軽減する特例があります。
また、相続人が未成年者であるなど一定の要件を満たす場合には、
税額を加算・減算する特例がありますので、
これらを考慮して各相続人毎の最終的な納付税額が決まります。
ところで、相続税の税率は
「図2:相続税の税率構造図」のように10%〜50%で、
財産額が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みになっています。
この仕組みを累進税率といい、
【ステップ1】で相続税計算上仮に按分計算した額毎に
それぞれこの累進税率を乗じます
(つまり、課税対象となる全財産をひとまとめにして
累進税率を乗じるのではありません。
故に、法定相続人が多い程、累進はおだやかになります)。
次に、相続財産が1億円又は2億円
又は5億円だった場合において、
相続人の数が増えると
どの位税額が減少するかをみてみましょう。
1.相続人が子供1人だけのケース
相続人が子供1人だけの場合は、
財産額が増えるほど次のように税負担率が高くなっていきます。
| 課税価格(a) |
相続税(b) |
税負担率(b/a) |
| 1億円 |
600万円 |
6% |
| 2億円 |
3,900万円 |
19.5% |
| 5億円 |
1億7,300万円 |
34.6% |
2.相続人が子供2人のケース
相続人の数が1人増えて2人の場合には、
基礎控除額が1,000万円増え、
かつ【ステップ1】における計算の為の
1人あたりの仮の取得金額が減少することに伴ない
累進税率が緩和されるため、
財産額が同じでも1に比べて税額は減少します。
| 課税価格(a) |
相続税(b) |
税負担率(b/a) |
| 1億円 |
350万円 |
3.5% |
| 2億円 |
2,500万円 |
12.5% |
| 5億円 |
1億3,800万円 |
27.6% |
上記(1)(2)のケースは相続人が子供だけのケースでしたが、
相続人に配偶者がいるケースにおいては
「配偶者の税額軽減の特例」があるために
税負担は大幅に減ります。
参考までに、相続人が配偶者と子供1人のケースで
配偶者が法定相続分(このケースでは2分の1)を
相続なさった場合の相続税の具体額を示しておきます。
<相続人が配偶者と子供1人のケース>
| 課税価格(a) |
相続税(b) |
税負担率(b/a) |
| 1億円 |
175万円 |
1.75% |
| 2億円 |
1,250万円 |
6.25% |
| 5億円 |
6,900万円 |
13.8% |
※相続税は配偶者の税額軽減後の金額です
このように、相続税は、
基礎控除と累進税率という仕組みにより、
財産額が同じでも、
相続人の数や配偶者がいるかどうかなどにより税額が変わります。
一般的には、相続人の数が多いほど税負担は軽くなりますし、
配偶者がいて財産を取得した場合には、
「配偶者の税額軽減の特例」が適用できるため
税負担は軽くなります。
また、相続人の構成が同じでも、
財産額の多寡により税負担率が変わります。
財産額が多いと適用される税率が高くなるため、
税負担は重くなります。
<図1>
<図2:相続税の税率構造図>
執筆:税理士法人 山田&パートナーズ税理士 壽藤里絵
監修:公認会計士 山田淳一郎
|