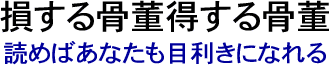|
第47回
商品学(ベトナム編)
2.ベトナム陶磁 I―混乱はチャンス!
ベトナム陶磁の最も古いものはドンソンの土器であろう。
窯を用いて焼かれた陶磁器としては
中国の後漢時代の作品とよく似たものがあり、
1980年年代から次々と発見されている。
これらの陶磁はベトナム人が作ったと言うよりは
ベトナムに移り住んだ中国陶工の手によるものかもしれない。
1991年ベトナムは開放政策に転じ外国人の入国を認めた。
わずかに開いた竹のカーテンを潜り抜けた
僕の骨董ハンティングを紹介しよう。
旧南ベトナム政府の大統領府近く、
ドンコイ通りをメコン河に向かってぶらぶらと歩いていた。
解放政策が始まってわずか2ヶ月後だと言うのに、
この通りにはもう5,60軒の骨董屋が店開きをしていた。
どこの国でも混乱から立ち上がり
復興の槌音が聞こえ出すと、
メインストリートに外国人目当ての店が開かれる。
最初に店を出すのは骨董屋とレストランである。
この通りもその例にたがわず、骨董屋が店開きをしていた。
どの店にも土まみれで手入れが行き届かない
掘り出したばかりの陶器や銅器が並んでいた。
その中に中国漢代の耳盃と全く同じものがあった。
「親父さん、これ中国のもの?」
「さあ、ワカリマセン」
俄仕立ての骨董屋は経験も何もない。
土が付いているので古いものだと言って売っているだけだ。
だからこの通りの骨董屋の商品は
全部自分が判断して買い付けなければならない。
僕が取り上げた耳盃の辺りにも
脚付きの壷や首の長い瓶などがごろごろ転がっていた。
僕の顔色を店主がじっと伺っている。
どうやら客の表情で値段を決めるつもりらしい。
南ベトナム人はベトナム戦争以前、
東南アジア一の商売人といわれていた。
「この作品は全部同じところから出たものです」
と土間の土器を指差しながら言う。
「アンタが掘ったん?」
「いいえ、ハノイの堀屋がそう言ってました」
戦争で負けた南ベトナムの商売人が、
戦争で勝った北ベトナムの古墳を
ところかまわず掘り返させているらしい。
歴史の皮肉と言うヤツだ。
耳盃は中国の漢代から晋くらいにかけて
たくさん作られている。
殆どが緑釉か青磁である。
しかし目の前にある耳盃は灰釉と言って、
やや白い土に灰釉をかけただけのシンプルなもので
今までに見たことのないタイプだった。
その作品に水を掛けてみると
プーンと土臭い匂いが小さな店内に漂った。
「これは絶対に古い」と直感した。
他の壷や皿にも水を付けてみたが
皆同じように古陶磁の証である匂いがブンブンとした。
「これいくら?」
「30ドルです」
むちゃくちゃに安かったが
一応半分に値切ってみたらすんなりと言い値になった。
なんか得したような、損したような複雑な気持ちに陥った。
そこで土間の10点ほどの品物全部をまとめて買うからと言うと、
「300ドルでどうか」というのだ。
先ほど半分で「いいですよ」と言われてしまったので
今度は三分の一の「100ドルでどう?」と
かなりきびしい線を出した。
また「いいですよ」と言われてしまった。
当時のベトナムでは喉から手が出るほど外貨が欲しかったのだ。
特にドルさえあればどんなことでも可能だった。
後日この骨董商の人たちの中から
ホテルの経営者、貿易業や、レストランなど
ビッグビジネスを立ち上げて成功している人たちが出ている。
ベトナムでいち早く外国人に接し資金を入手するのは
骨董が一番手っ取り早かったのだ。
明治維新の日本、戦後の混乱期におけるビジネスも
同じようなものだ。
|