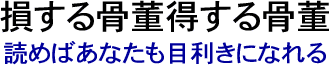
「骨董ハンター南方見聞録」の島津法樹さんの
道楽と趣味をかねた骨董蒐集の手のうち
|
第43回 今から34年前マニラのある骨董屋で 12世紀初頃のちょっといい感じの磁州窯の皿だった。 二十数年後にその皿とは日本のさる所で再会した。 しかし、磁州窯の中にも北宋期の白磁黒釉掻き落しのような |
| ←前回記事へ | 2004年11月8日(月) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
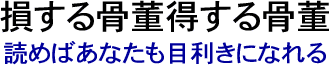
「骨董ハンター南方見聞録」の島津法樹さんの
道楽と趣味をかねた骨董蒐集の手のうち
|
第43回 今から34年前マニラのある骨董屋で 12世紀初頃のちょっといい感じの磁州窯の皿だった。 二十数年後にその皿とは日本のさる所で再会した。 しかし、磁州窯の中にも北宋期の白磁黒釉掻き落しのような |
| ←前回記事へ | 2004年11月8日(月) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |