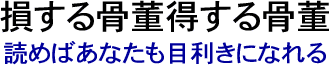|
第31回
商品学(中国陶磁編)
2.漢緑釉(2) 殆どの人が損した作品
買っても買っても漢緑釉の作品は尽きない泉のごとく
滾々と中国大陸から湧き出てくるのだった。
とうとう10万円を割ってしまう大壷も出てきた。
あるコレクターなど、この時期に相場を張るみたいに
漢緑釉を買い集め200個近く買った人もいたらしい。
その人は
「2000年も前に作られた本物の漢緑釉の壷が、
30万や40万で入手できるなら
中国大陸にある緑釉の壷を全部買ってやる」
と豪語していたらしい。
が、さすがに200個を超えると置き場所に困り、
奥さんにいやみも言われるのでやめてしまった。
この話は本人から直接聞いたことだ。
あまり値下がりすると僕も買う気をそがれ、
またお客さんにも迷惑がかかるのでこの種のものの仕入を控えた。
中国人ディーラーに聞いてみると
漢の墳墓は埋蔵品が桁違いに多いらしい。
1箇所の古墳を発見すると
膨大な量の陶磁器が出てくると言っていた。
後漢時代は中国の歴史上でも最も厚葬の風があって、
大壷だけでなく生活に密着した様々な造形の作品が作られている。
緑釉や褐釉の豚舎や城塞、水禽、竈、井戸、
犬や豚、楽人たちを見ていると、
漢代の人々の生活を覗き見しているようで興味深い。
これらの作品は嘗て古代の人々の生活を知る重要な資料として
世界中の美術館が蒐集して展示したものだから
コレクターも競って買い求めた。
日本の古美術品といえば茶の湯の道具、
あるいは仏教美術といわれるところが中心だったが、
昭和初期に中国の発掘陶磁が渡来し、
鑑賞陶器というジャンルが確立され、一大ブームを巻き起こした。
この時は古墳の発掘もごく小規模であった為、
当初低かった値段も急カーブで上昇したという。
以降戦後長い間、中国本土の発掘は全く止まってしまい、
価格は高値安定が続いていた。
そこへ降って沸いたように文革で各地の古墳が発掘され、
多くの副葬品が現れた。
ちょうどその頃市場経済の導入によって拝金主義が生まれたため、
古美術品の流通が大きくなったのだ。
しかし、コレクターはこれ一つだと思うから買うのであって
同じようなものがどんどん出てくると、
どんなに安くても購入を躊躇してしまう。
飽和点に達した漢緑釉の作品が元の価格に戻るのに
10年は十分かかるだろう。
しかし、2000年も前の素晴らしい文化財が
20,30万で購入できるのだから、
良いものを選んで買っておけばきっと楽しい夢が見られる。
|