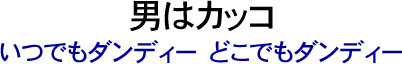|
第669回
ローマ数字のおしゃれな計算
ローマ数字を書けますか。
もし書ける方はどうか怒らないで下さい。
1、2、3・・・というアラビア数字に対して
I、II、III・・・と書く数字のことですね。
広く知られているように、
アラビア数字よりもローマ数字のほうが、
はるかに古い歴史を持っています。
英語で「計算する」の
“カリキュレイト”caluculate は、
ラテン語の“カルキュルス”caluculus が語源。
これは「小石」の意味です。
むかしの人びとは朝晩、
自分が飼っている家畜の数を確認した。
この時、10頭づつに小石を置いて、
間違えないようにしたのです。
I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X、
XI、XII、XIII、XIV、XV、XVI・・・
となるわけです。
すでにご存じの方は復習になりますが、
しばらくおつき合い下さい。
つまり5は「V」、10は「X」で示されるわけです。
どうして「V」が5を意味するのか。
これは片手を大きく開いた形を示しているのです。
「X」は「V」をふたつ重ねた形だから
10の意味になるわけです。
そしてVの左側に I を置くと、引き算になります。
逆に右側に I を置くと、足し算になります。
「IV」は4、「VI」は6というわけです。
「X」についてもまったく同じ考えかたです。
では、数字が大きくなった時にはどうするのか。
もちろんちゃんと記号が用意されています。
「c」が100を、「M」が1000を意味します。
これもやはりラテン語の
“セントゥム”centum 、
“ミッレ”mille が
それぞれの語源となっています。
これらの記号を組合わせれば、
たいていの数字を示すことができるわけです。
ただしひとつだけ例外があります。
時計の文字盤。
この場合に限っては「4」は「IIII」と記される。
ある国の、ある王様がたまたま四世であり、
V から I をひくのは縁起が悪いと、
許さなかったからです。
この伝統以来、時計だけは例外的に
「IIII」が使われているのです。
|