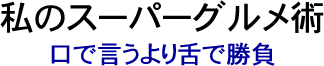|
第153回
純米無濾過生原酒は一時の流行か?
その3 アルコール添加の功罪
日本酒にアルコール添加が大々的に行われるようになったのは、
昭和14年の満州での実験に起源を発する。
日本軍の士気高揚のために
日本酒の増産が必要となっていたが、
戦争前の米不足でアルコールで増量する研究が行われ、
満州の千福酒造が受けて完成させた。
これが、昭和16酒造年度には
満州での日本酒へのアルコール添加が許可され、
日本本土にすぐに伝わり、
昭和23年の大腐造をきっかけに、
国が率先して各地の蔵にアルコール添加を呼びかけるようになる。
つまり、70年ちょっと前までは、
日本酒といえば米と米麹と水だけで造られていた。
江戸時代に柱焼酎といって、
日本酒の醪桶に焼酎を添加して、腐造をふせぎ、
酒をしゃきっとさせる技法が試みられてはいたが、
だいたいは純米造りであった。
これが、昭和24年にはブドウ糖、水飴、コハク酸、
乳酸、グルタミン酸ソーダなどを
30%のアルコール液に溶かした調味液を作り、
それを上槽前に醪に加えた酒造りがされるようになった。
純米の造りの三倍に量を増やせるので、三増酒と呼ぶ。
この頃は戦時中、戦後の緊急避難として、
アルコール添加、調味液添加が奨励されたが、
その後の昭和、平成の豊かな時代になっても、
まだ廃止はされていない。
国税庁が発表している
平成15醸造年度の清酒製造に関わるデータを見てみると、
清酒全体の製造量は約61万キロリッター、
そのうち米だけで造る「純米酒」と「純米吟醸酒」、
「純米大吟醸酒」は合計で
約7万5千キロリッターしか造られていない。
逆に、アルコール添加で大きく増量した「普通酒」は
32万キロリッター、
さらに調味液による「三増酒」は
10万キロリッターも造られている。
つまり、純米造りは全体の一割強にすぎず、
三増酒よりも少ない。
しかし、純米酒ならすべていいかというと、そうでもない。
同じ蔵のアルコール添加の日本酒のほうが美味しい場合も多い。
これは、純米酒はアルコール添加酒に比べて
造りが難しいからだ。
醪状態で最後のほうにアルコール添加を行うと、
すっきりとした軽やかな酒質にすることができる。
純米酒はとかく重たい酒になりやすい。
それは、造りの原点である、
原料米処理、麹造り、酒母造りがうまく行っていない場合に多い。
つまり、きちっと造った純米酒なら
アルコール添加酒よりも旨みを出し、
かつ切れもある酒質が可能なのだが、
蔵の造りの技術が不足していたり、
造る手間を省いたりすると、
かえって重たい、もったりした酒になるわけだ。
純米酒がいいか、アルコール添加酒がいいかという議論は、
長いこと日本酒好きの間ばかり、業界でも議論されている。
埼玉県の燗にして旨い酒「神亀」は昭和62酒造年度に
全て純米造りとなった。
以来、神亀酒造の小川原専務は純米だけを造り続けている。
一方、静岡の銘酒「開運」を作っている
土井酒造場の土井社長は
アルコール添加は昔からの柱焼酎の歴史にうらうちされていて、
酒を軽やかにするには必要な技法ととらえている。
私はどちらかというと、
しっかりと造った純米酒のほうが好きだが、
それは、熟成したときにアルコール添加酒は
どうしても添加したアルコール分子が
浮いている感じがすることが大きい。
純米酒でないと酒ではないと極論はしないが、
熟成した旨みを楽しむには、純米無濾過生原酒が面白い。
|